

佐賀の中学生が海洋プラスチックから学ぶ特別授業の成果とは
学びの場を超えた実践:佐賀の中学生の海洋プラスチック特別授業
2025年10月16日、佐賀県唐津市の佐志中学校で特別な授業が行われました。この授業は、海洋プラスチックごみをテーマにしており、3年生の生徒たちにとっては特別な意味を持つものでした。特定非営利活動法人「唐津Farm&Food」が主催し、生徒たちに海洋ごみの現状、ならびにそれに対する対策を学ぶ機会を提供しました。
海洋プラスチックの現状とその重要性
生徒たちは授業の中で、まず海洋プラスチックごみの現状について講話を受けました。唐津Farm&Foodの代表者が、プラスチックごみの発生源やその影響、そしてそれに対する対策の必要性を強調しました。この授業はただの学びの場ではなく、自分たちの生活や地域に直結する問題であることが伝えられ、生徒たちの意識が高まりました。
アップサイクル体験:ペットボトルキャップを使った新しい創造
この特別授業では、午後に実施されたワークショップが特に印象的でした。生徒たちは自らデザインした金型を使い、回収したペットボトルキャップを“船”の形にアップサイクルしました。キャップを溶かして射出成形するという工程で、教員や校長も参加し、笑顔と驚きの声が上がりました。
新しい形に生まれ変わったキャップを目にした瞬間、彼らは環境保護の大切さを実感し、身近な素材が再利用される喜びを体験しました。「海の環境を守るための行動は、小さなモノづくりから始まる」とのメッセージが伝わる瞬間でした。
デジタル絵馬で想いをつなぐ
授業の締めくくりには、金沢美術工芸大学が制作したアニメーション『おとーしゃ』を観賞し、海と人とのつながりについて感じる時間が設けられました。その後、大阪・関西万博「対馬WEEK」で使用されたデジタル絵馬にて、生徒一人ひとりが未来の海に向けた願いを書き込みました。この体験を通して、学び、感性、行動がつながる意義が再確認されました。
唐津の取り組みと未来への展望
唐津Farm&Foodは、今後も県内外の学校や企業、自治体と連携し、持続可能な社会のための教育(ESD)を推進していく計画です。ワークショップや講話を通じて、アップサイクルや発生源の削減に向けた具体的な取り組みを拡充していくことで、地域の環境意識がさらに高まることが期待されます。
この特別授業は、単なる知識習得に留まらず、生徒たちが積極的に行動し、地域を変えていく力となる一歩を踏み出すきっかけとなりました。
海洋プラスチック問題は世界的な課題ですが、佐賀の中学生たちの参加によって、この問題に対する地域発のアクションが一つずつ形になっていくことを期待します。未来の海を守るための第一歩、彼らの取り組みがその礎となることを信じています。







関連リンク
サードペディア百科事典: アップサイクル 唐津Farm&Food 海洋プラスチック
トピックス(その他)




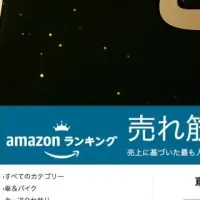





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。