

新薬開発プロジェクトを変革するBacklogの活用法
新薬開発プロジェクトを変革するBacklogの活用法
医薬品開発は、複数の部署が協力して行う長期にわたるプロジェクトです。その中で、株式会社三和化学研究所は、プロジェクト管理ツール「Backlog」を導入し、従来のやり方を一新しました。この改革がもたらした変化と成果を詳しく見ていきましょう。
導入の背景
新薬の開発は、研究から生産、マーケティング活動に至るまで、多くの部署が密に連携を図る必要があります。しかし、三和化学研究所では、従来Excelでの管理が主流で、進捗の共有が困難でした。そのため、部署間の連携において課題が多く、効率的なコミュニケーションが成り立っていませんでした。このような背景から、同社は「Backlog」を導入する決断を下しました。
目指すべき環境
新たに構築すべき環境とは、タスクと進捗をリアルタイムで可視化し、メンバー全員が共通の理解を持てる体制です。「Backlog」を導入することで、誰が、何を、いつまでに実施するのかを明確に共有する仕組みが実現しました。
Backlog導入による効果
1. 会議の生産性向上
Backlogでタスクの進捗を常時共有できる体制を整えた結果、定例会議での進捗報告が不要になりました。これにより、会議の時間はただの報告から議論へと変化。プロジェクトメンバー同士がより建設的な議論を行い、意思決定の場としての質が向上しました。
2. 意識の統一
Backlogにおける課題の担当者や期限を明確にすることで、部署を超えたメンバー間での共通理解が浸透しました。以前は同じ会議でも、それぞれのメンバーが異なる認識を持つことが多かったですが、可視化が進んだ結果、情報の行き違いが解消。連携作業がスムーズになっています。
3. サポートシステムの活用
「Backlog」の導入時には、ヌーラボの提供する「あんしん!Backlog導入支援プログラム」をフル活用しました。データ移行やルールの設定を丁寧にサポートすることで、早期の運用定着を果たしました。また、導入の目的をチームで明確に共有することで、ツールが単なる手段ではなく、チーム全体の業務スタイルを変革するきっかけとなり得ました。
三和化学研究所の展望
三和化学研究所の経営企画グループの村瀬様と小西様は、Backlogはスケジュールやタスク管理だけでなく、コミュニケーションを強化するためにも非常に有効であると述べています。新薬開発プロジェクトだけでなく、全社での活用も充実していく見込みです。
彼らは、組織内で「バックログスイーパー」のような役割を持つ存在が、定着の鍵とされることを実感しており、感謝や協力を自然と伝え合える文化の構築を目指しています。これは今後の多様化する労働環境にも対応可能なチームワークマネジメントへとつながります。
結論
「Backlog」を通じて、株式会社三和化学研究所はプロジェクトの推進体制を見事に変革しました。今後も、業務環境に応じたBacklogの活用を進め、多種多様なチーム構成によって作業効率を向上させることが期待されています。更なる改革の進展が楽しみです。




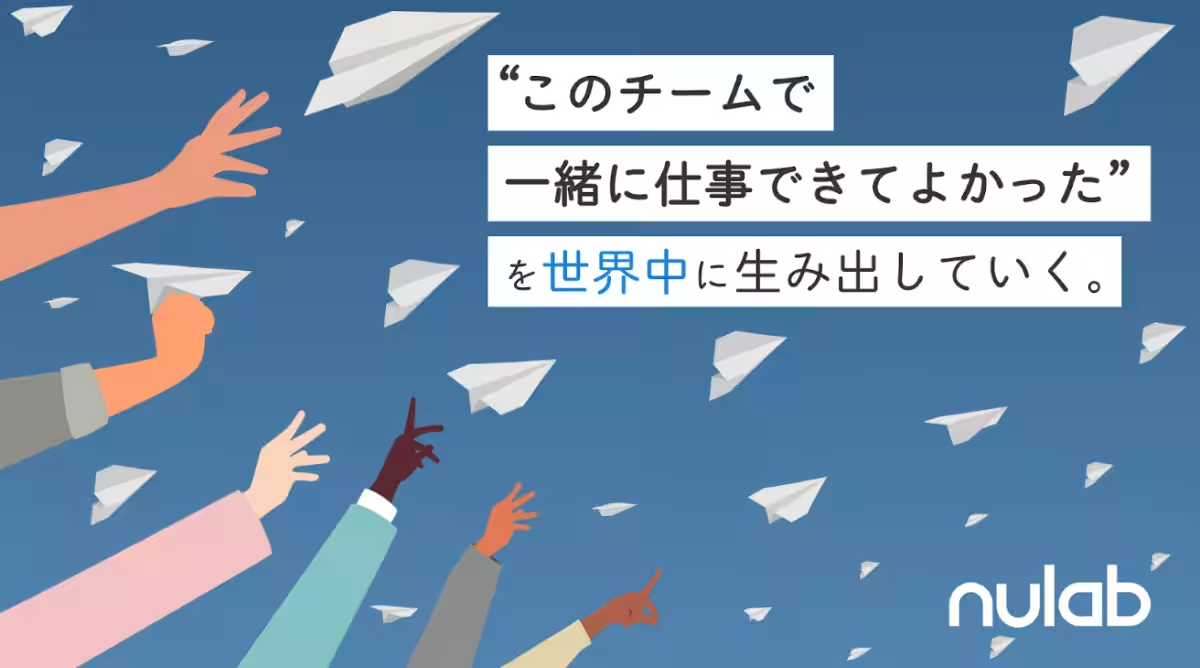
トピックス(その他)






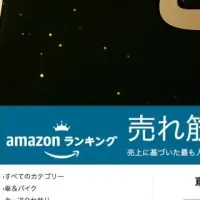



【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。